警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットな…
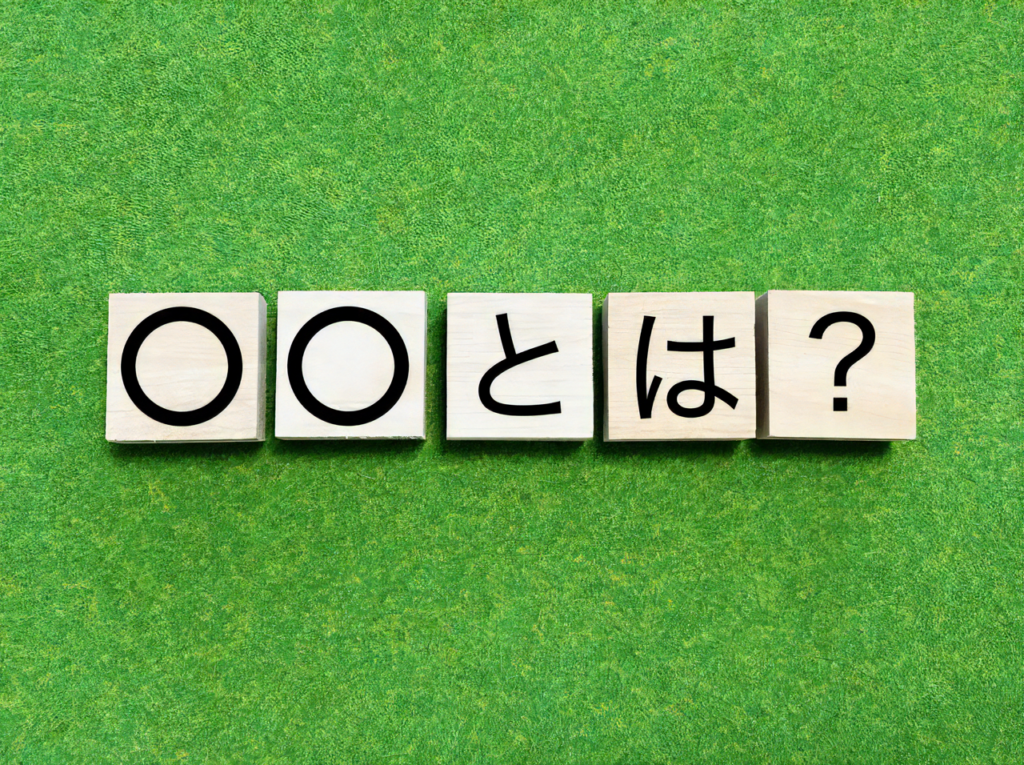
どのような業界にも専門用語がありますよね。その業界に飛び込もうと思ったとき、専門用語の壁にぶつかるという経験は多いはず。
警備員として働く際、もしくは警備会社などに警備を依頼する際に、馴染みのない用語に戸惑うという方も少なくありません。
あらかじめ警備に関する用語について把握しておくことで、スムーズに業務を身につけられたり、自身の希望通りの警備を依頼しやすくなったりするなどのメリットもあります。
この記事では、警備および警備業務において使われる用語について解説します。
目次
まずは警備業務の分類に関する用語から解説します。
警備業務は、警備業法に基づいて仕事内容によって1~4号業務に分類されているのが特徴です。
警備会社によって、1号業務は扱っているが3号業務は扱っていないなどの差があるため、警備を依頼したい場合には必須の知識となります。
関連記事:「警備を依頼したい!業務の種類や料金相場・警備会社を選ぶポイントを解説」
1号業務は「施設警備」や「巡回警備」に分類される業務です。
企業や商業施設、病院やマンションなどの施設内での警備を行なうのがおもな仕事です。
施設内を巡回することにより、不審者や危険物の有無を確認するほか、施設の出入口での人や車両の管理、防犯カメラ映像の監視なども業務内容に含まれます。
以下は1号業務に該当する警備業務です。
関連記事:「施設警備とは?ビルや商業施設などでの仕事内容や年収、将来性をまとめて解説」
関連記事:「事件や事故を未然に防ぐ「1号警備」とは?業務内容や警備を実施するメリットを紹介」
2号業務は、「雑踏・交通誘導警備」に分類される業務です。
工事現場や建設現場、イベント会場などで交通誘導や雑踏整理を実施し、歩行者や車両による事故やトラブルの発生を未然に防ぐのがおもな業務です。
以下は2号業務に該当する警備業務です。
関連記事:「2号警備とは?交通誘導・雑踏警備の業務内容や依頼時のポイントを紹介」
関連記事:「イベント警備とは?対応業務の内容や警備会社の選び方も解説」
関連記事:「雑踏警備と交通誘導警備は何が違う?仕事内容や違いを解説」
3号業務は、「運送業務」に分類される業務です。さらに「貴重品運搬警備」と「核燃料物質等危険物運搬警備業務」の2つに分けられます。
関連記事:「3号警備とは?依頼できる警備内容や1号・2号・4号警備との違いなどを詳しく解説」
関連記事:「輸送警備とは?年収相場や志望動機の書き方も解説」
4号業務は「身辺警備」に分類される業務です。
いわゆる「ボディーガード」と呼ばれる警備業務で、要人や芸能人、契約者である一般市民などの周囲を警戒し、身体の安全を守るのが仕事です。
近年では、政治家などの有名人だけでなく、ストーカー犯罪対策や子ども、高齢者などの外出を見守るサービスなどが提供されるケースも少なくありません。
関連記事:「身辺警護とは?向いている人の特徴や働くうえでの注意点も解説」
関連記事:「4号警備とは?身辺警備の業務内容や要人警護との違いを解説」

警備員が使用する道具や装備には、見慣れないものもたくさんあります。
ここでは、警備業務に用いる道具や装備に関する用語について解説します。
関連記事:「警備員の装備品とは?基本的な服装や業務別の装備品まで解説」
交通誘導の際に、車両に対して合図を出すために使う赤と白で1組の旗を赤白旗と呼びます。
左手に赤、右手に白を持つのが基本ですが、左右を入れかえることもあります。赤が「停止」、白が「進行」の意味を持ち、どのように誘導したいのかによって振り方が決まっています。
正式名称を「A型バリケード」と言います。工事現場・建設現場などにおいて通行止めとして用いられる「A」の形をしているのが特徴の折り畳み式のバリケードのことです。
フェンスを用いてバリケードを作る場合は「Bバリ」と呼ばれます。
「大看板」と呼ばれることもある、工事現場などに設置されている看板を「件名版」と呼びます。
工事の内容や期間(日程)、実施する時間帯などの詳細が記載されています。
件名版を書くことで、歩行者や車両の誘導をより安全に行なうことができます。
不審者に襲われた際などの危険時に自分の身を守るために所持している棒を「警戒棒」と呼びます。
警備業法によって長さと重量が決まっており、携帯するには届け出をしなければなりません。
あくまでも護身用のものであり、緊急時に使用する場合は必ず打撃が必要最低限であるように指導されます。
ここからは警備業界で働くと頻繁に耳にする、業務内でよく用いられる用語について解説します。
警備業法とは、警備に関する規則をまとめた法律で、警備員や警備会社が守らなければならない規定のことです。
以下は警備業法で規定されている項目の一例です。
警備業に携わる警備員や、警備員を雇用する警備会社は、すべてこの警備業法に従わなくてはなりません。
関連記事:「【企業担当者向け】警備業法とは?違反の事例や原因、警備会社を選ぶポイントも解説」
警備業務においては、警備の種類によって検定合格警備員の配置人数が決められています。
この基準のことを「配置基準」と呼び、検定合格証明書を取得済に警備員の一定数の配置が必要となります。
関連記事:「交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会社に依頼すべき理由も解説」
ポストとは、警備員を配置する場所のことを指します。
ポストの場所を詳細に記載した表は「ポスト配置表」と呼ばれます。
警備業務の開始・終了を会社に報告することを「上番(じょうばん)」「下番(かばん)」と言います。
上番は「業務開始」の意味であり、下番は「業務終了」の報告を表します。
「片交(かたこう)」とは「片側交互通行」のことです。
道路工事などで、1車線のみで車両を通行させるために行なう交通規制を指します。
工事内容によって、一般車両が走行できる幅を2車線分確保できない場合に行ないます。おもに2号警備で用いられる用語です。
「開放」は道路工事などが終わったあと、道路を車両や歩行者が通行できるように元通りに戻すことを指します。
前述の片側交互通行の交通規制を取り除くことも「開放」に該当します。
通常、警備における勤務時間は8時間のケースが多いです。そのため、現場における拘束時間が4時間の勤務形態のことを「ハーフ現場」と呼びます。
半日しか業務に就けない方に向いている勤務形態といえます。
オフィスビルや商業施設の出入口など、指定の場所に立ち警備をする警備方法を「立哨(りっしょう)」と呼びます。
空港やイベント会場といった混雑が予想される場合で用いられるケースも多いです。
一方で、座って警備を行なう場合は「座哨(ざしょう)」と言います。

警備業務は資格がなくても行なえますが、警備業務に関する国家資格も複数存在します。
ここでは、警備業務に関する資格・教育において用いられる用語を解説します。
警備業務検定とは、前述の警備業法において実施を定められている資格検定試験のことで、合格すると国家資格の取得が可能となります。
検定は警備分野ごとに6種類、それぞれ1級と2級に分かれています。
2級はだれでも受検することができますが、1級受験のためには2級合格および該当警備業務に一定期間以上の従事が条件となります。
警備業務検定の合格によって、有資格者でないとできない業務への対応が可能になるため、警備員としてのキャリアアップを目指しているのなら取得をおすすめします。
関連記事:「警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットなども解説」
警備員指導教育責任者講習は、警備員の指導・教育を行なうために求められる資格です。
講習受講後、修了考査に合格すると取得できます。
ただし、受講区分に該当する警備業務に一定期間従事していることや、前述の警備業務検定1級に合格していることなど、講習の受講には条件があります。
関連記事:「警備員指導教育責任者とは?警備員の資格とスキルアップについて解説」
新任研修とは、警備員として働くために最初に受ける教育のことで、正社員、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらずすべての人が必ず受けなければなりません。
新任研修では、警備の仕事に携わるために必要な知識や心構えなどを学びます。
警備業法において、基本教育10時間以上、業務別教育10時間以上の併せて20時間以上が必要とされています。
新任教育における指導は、前述の警備員指導教育責任者が担当するのが決まりです。
関連記事:「警備員の新任・現任研修の内容とは?役立つ資格やよくある質問についても解説」
警備員として働いている人が、年間を通じて受けることを義務づけられているのが「現任教育」です。
警備員として知識や能力の維持・向上を目的に行なわれ、法改正などの新しい知識の習得や業務内容に応じた必要な知識、技能を学びます。
現任教育では、年度ごとに10時間以上の教育を受ける必要があります。
内容は警備業法により、基本教育4時間以上、業務別教育6時間以上と定められています。
関連記事:「警備員の現任教育とは?教育時間・内容や知っておきたいポイントを詳しく解説」
警備員として働きたいとお考えの方、および警備会社に警備のご依頼を検討中の企業担当者の方に向けて、SPD株式会社の警備の強みについて解説します。
SPD株式会社では、おもに「交通誘導を含めた常駐警備」と「イベント会場などでの交通誘導警備」の2つの業務を提供しています。
正社員をはじめ、契約社員やパート・アルバイトなど、年齢制限を設けず幅広い人材を募集中で、あなたのライフスタイルに合った働き方もきっとみつかるはずです。
社員のワークライフバランスを重視ているため、プライベートも犠牲にはさせません。
各種資格取得制度なども充実しているため、未経験・無資格からでも警備員としての業務をスタートできます。
SPD株式会社では、警備において企業担当者の方をはじめとしたお客様が求めているニーズを調査、分析し、長年培ったノウハウをもとに最適なプランをご提案しています。
有資格者も多数在籍しているため、依頼内容に応じて、各種資格を取得している警備員の配置も可能です。
対応している警備事業は、おもに「常駐警備」と「イベント・交通誘導事業」の2つです。
警備の業務に関する用語をまとめてご紹介しました。
これから警備員として働きたい方は、事前にこれらの言葉を知っておくと、スムーズに業務を始められます。
また、警備を依頼したいとお考えの方も、希望通りの依頼をしやすくなります。
警備員として働きたい方、警備の依頼をしたい企業担当者の方は、ぜひお気軽にSPD株式会社にご連絡ください。
この記事をシェアする
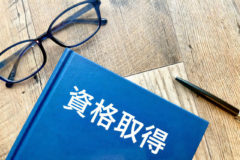
警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットな…

イベント警備とは?対応業務の内容や警備会社の選び方も解説

常駐警備とは?業務内容と警備会社へ業務を委託するポイント…

イベント会場等の警備員に必須の雑踏警備2級とは?企業様向…

交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会…

警備会社に警備を依頼する方法は?依頼までの流れやポイント…

警備を依頼したい!業務の種類や料金相場・警備会社を選ぶポ…

警備会社に駐車場管理を依頼する目的とは?依頼先の選び方を…

ガードマンに依頼できる警備業務とは?料金相場や警備会社を…

警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

交通誘導1級と2級の違いとは?取得のメリット・試験内容・…

工場における警備員の業務内容や勤務形態とは?おすすめの警…

警備会社の料金相場は?料金の変動要因や警備会社の選び方も…

交通誘導2級とは?未経験から資格を取得する方法も解説しま…
関連する記事はありません
