警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットな…

交通誘導警備員を配置する際には、道路の種類や場所、状況により、警備業法で「配置基準」が定められている場合があります。
配置基準を遵守するには、警備に関する有資格者を配置しなければなりません。有資格者配置の必要がある場合には、警備会社への依頼がおすすめです。
この記事では、交通誘導警備員の配置基準の概要や指定路線情報、また、警備会社へ依頼するメリットや警備会社の選び方などについて紹介します。最後に、ご質問の多い内容をFAQ形式でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
動画でご紹介!交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会社に依頼すべき理由も解説
※記事の要点を凝縮して4-5分程度でご覧頂けます
警備業法の規制の一つに「配置基準」があり、特定の業務には、資格を持つ警備員を配置しなければならないとされています。
特定の業務とは、以下の1および2に該当するものです。
上記業務を行なう場合、業務の種別ごとに警備業法第23条第4項の合格証書が交付されている警備員を必要人数配置し、業務を実施しなければなりません。
国家資格である「警備業務検定」の合格者は「検定合格警備員」とも呼ばれ、警備業法第23条第4項の合格証書が交付されます。
おもな警備業務の資格は次の6種類で、それぞれ1級と2級があります。
警備業務の内容によっては、上記国家資格を持つ警備員を必要数配置しなくてはならないことを覚えておきましょう。
ここでは交通誘導警備業務の配置基準について、具体的に解説します。
交通誘導警備業務とは、イベント会場や駐車場、工事現場など通行に危険のある場所において、車や歩行者が安全に通行できるように誘導する業務のことです。
事故を防ぐために交通誘導警備を行なう際は、配置基準にしたがって、交通誘導警備業務検定1級または2級の有資格者を配置しなくてはなりません。
交通誘導警備業務検定1級または2級を取得した警備員は「交通誘導警備員(A)」と呼ばれ、「検定合格警備員(A)」と表されることもあります。一方で、資格のない交通誘導警備員は「交通誘導警備員(B)」と呼ばれます。
有資格者=交通誘導警備員(A)を配置する必要があるのは、次のような場合です。
1・2いずれの場合も、業務を行なう場所につき、上記検定の有資格者を1人以上配置するよう定められています。
また、配置基準に違反した場合には、警察の行政処分の対象となるため注意が必要です。配置基準を遵守し、安全に交通誘導警備業務を行なえるよう心がけましょう。
交通誘導警備員(A)の配置が必要な指定路線は、各都道府県の公安委員会によって定められており、警察のサイトで確認できます。
以下は、主要な都道府県の指定路線情報のリンクページです。
【主要都道府県の指定路線情報のリンクページ一覧】
※2025年6月10日時点

警備を行なうには、現場の状況に応じた専門的な知識やスキルが求められます。自社の従業員だけで対応しようとしても、安全性を十分に確保できないケースもあるでしょう。
また、警備を行なう場所や道路によっては、自治体の条例や要項などで交通誘導警備員の配置が義務付けられています。特に前述の指定路線では、警備業法に基づき、資格を有した交通誘導警備員(A)を配置する必要があります。
そのため、交通誘導警備などの有資格者が在籍している警備会社に警備を依頼することが、安全確保のうえでも重要です。
以下で、警備会社に交通誘導警備を依頼するメリットを解説します。
一般的に警備会社には、警備業務検定の資格保有者が多く在籍しています。そのため、配置基準を遵守する必要がある道路や現場でも、迅速に対応することが可能です。
加えて、想定以上に警備の人数が必要な場合も、警備会社に依頼することで適切な人数を確保できます。
警備会社では研修制度や資格取得支援制度を整えて、警備員のスキルアップや資格取得にも力を入れているため、安心して依頼できるでしょう。
交通誘導警備員を配置すれば、信号無視など事故につながりかねない危険行動を抑制することが可能です。人流が整理されることで、事故の未然防止にもつながるでしょう。
また、駐車場などでの車両誘導警備では、事故を防ぐだけでなく、スムーズな駐車・出入りも可能になります。
警備会社に警備を依頼すれば、プロの視点によるアドバイスを受けられ、必要な安全策を吸収できることもメリットといえるでしょう。
※SPD株式会社では交通誘導の一部警備のみ(駐車場誘導やイベントに関わる交通誘導警備並びに雑踏警備業務)を取り扱っております。
警備会社に業務を委託すれば、これまで固定費として発生していた人件費を、必要なときだけ支払う変動費に置き換えられるため、自社の従業員が警備業務に従事するのに比べて人件費を削減できます。
また、自社で警備を行なうとなると、資格取得をはじめ人材育成に多くの時間と労力が必要となる点も懸念されます。その点、警備会社に依頼すれば、即戦力となる人材をすぐに配置できるため、育成にかかる負担を軽減できます。
さらに、浮いた時間や人材を別の業務に振り分けることができるため、全体としての業務効率化にもつながります。
こうしたメリットを考慮し、すべてを自社従業員で対応するのではなく、警備のプロがそろっている警備会社への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

交通誘導警備を依頼する際には、以下の3つのチェックポイントを意識して警備会社を選びましょう。
警備会社によって、対応可能業務や得意業務は異なります。例えば、交通誘導警備のなかでも駐車場誘導やイベント会場の誘導がメインで、高速自動車国道や自動車専用道路の警備は対象外としているケースもあります。自社がどのような警備業務を依頼したいのかを明確にし、その業務の実績がある警備会社を選びましょう。
無資格の警備員では、配置基準を遵守できません。警備会社には警備業務検定資格の保有者が多く在籍していますが、依頼する際には、必要な業務に対応できる有資格者によって配置基準を守れるかどうか、しっかりと確認しておきましょう。
やむを得ず直前の依頼になったり、依頼内容に変更が生じたりすることもあるでしょう。そうした急な依頼に対しても、必要な警備員を柔軟に配置してくれる警備会社を選んでおくと安心です。
SPD株式会社は、オフィスビルやマンションの常駐警備、イベント会場・商業施設での交通誘導、雑踏警備業務などを実施している警備会社です。イベント会場での雑踏整理や車両の安全誘導、交差点などでの歩行者の保護、新店舗におけるオープン警備など、豊富な実績があります。
※建築・土木等に関連する交通誘導は、SPD株式会社では取り扱っておりません。
SPD株式会社では、豊富な実績と長年にわたり培ってきたノウハウによって、お客様の要望に合った警備プランをご提案します。従業員の資格取得にも力を入れており、必要に応じた有資格者の派遣、配置も可能なため、配置基準が気になる方も安心してご依頼ください。

ここからは、交通誘導警備の配置基準に関してよくある質問と、その回答を紹介します。事前に確認しておくことで、警備会社への依頼がスムーズになるでしょう。
交通誘導警備員AとBの違いは、交通誘導警備業務に関する資格の有無です。交通誘導警備業務検定1級または2級の取得者は、「交通誘導警備員(A)」や「検定合格警備員(A)」と呼ばれます。
一方、資格を持たない交通誘導警備員は、「交通誘導警備員(B)」と呼ばれます。
交通誘導警備員(A)の配置が必要な道路は、高速自動車国道・自動車専用道路、および各都道府県の公安委員会が定めた「指定路線」です。これらの道路で交通誘導警備にあたる際は、交通誘導警備員(A)を1人以上配置することが義務付けられています。
指定路線の情報については、各都道府県警のサイトに掲載されているので、必要に応じて確認するとよいでしょう。なお、主要都道府県の指定路線リンクページについては、本記事内で紹介しています。
交通誘導警備員(A)と(B)では、警備料金に違いがあります。国土交通省の資料によると、2025年3月より適用された東京都の公共工事設計労務単価は、交通誘導警備員(A)が2万200円、交通誘導警備員(B)が1万7,600円です。
また、平日昼間・実働8時間の交通誘導警備を依頼した場合、1人当たりの料金相場は1万6,000円~2万2,000円ほどとされています。実際の警備料金は、有資格者である交通誘導警備員(A)のほうが、3,000~5,000円ほど高くなることが一般的です。
参考:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」
警備会社の料金の相場や変動する要因について知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
警備会社の料金相場は?料金の変動要因や警備会社の選び方も解説
交通誘導警備を行なう場所によっては、警備業法で定められた「配置基準」を遵守し、有資格者を必要数配置しなければなりません。そのため、交通誘導警備員を配置したい場合には、有資格者が多数在籍し、交通誘導警備を得意としている警備会社に依頼するのがおすすめです。
オフィスビルやマンション、イベント会場、商業施設などでの警備実績が豊富なSPD株式会社には、警備業務検定の有資格者が多数在籍しているため、安心して交通誘導警備をご依頼いただけます。
お客様の要望に合わせたプランを提案することも可能なため、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事をシェアする
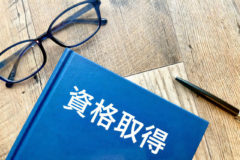
警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットな…

イベント警備とは?対応業務の内容や警備会社の選び方も解説

常駐警備とは?業務内容と警備会社へ業務を委託するポイント…

イベント会場等の警備員に必須の雑踏警備2級とは?企業様向…

交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会…

警備会社に警備を依頼する方法は?依頼までの流れやポイント…

警備を依頼したい!業務の種類や料金相場・警備会社を選ぶポ…

警備会社に駐車場管理を依頼する目的とは?依頼先の選び方を…

ガードマンに依頼できる警備業務とは?料金相場や警備会社を…

警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

交通誘導1級と2級の違いとは?取得のメリット・試験内容・…

工場における警備員の業務内容や勤務形態とは?おすすめの警…

警備会社の料金相場は?料金の変動要因や警備会社の選び方も…

交通誘導2級とは?未経験から資格を取得する方法も解説しま…
