常駐警備とは?業務内容と警備会社へ業務を委託するポイント…

警察の職種には地域警察、刑事警察などのさまざまな職種があります。交通巡視員は警察職員の職種の一つで、おもに交通関係の業務に携わります。
今回は、交通巡視員の役割や警察官との違い、おもな業務内容などを解説します。交通巡視員の仕事に興味がある方はぜひ参考にしてください。
目次
交通巡視員は、都道府県警察に置かれる職種の一つです。
警察官とほぼ同じ制服を着用して業務にあたりますが、警察官とは異なります。その名のとおり、おもに交通関係の業務に携わり、道路交通の安全性の維持管理に努めます。
昭和51年には、全国で約4,000人の交通巡視員がいました。しかし、現在では交通巡視員を廃止し、警察官と統合している都道府県もあり、全体数は大幅に減少しています。
交通巡視員に逮捕権や捜査権などは与えられておらず、警察官が所持を許可されている手錠や拳銃も所持できません。また、階級制度が適用されないため、階級章がないことも警察官との大きな違いです。交通巡視員の制服の左胸には、階級章と似たデザインの交通巡視員章が付けられています。
以上の特徴から、交通巡視員は、交通分野に特化した警察官のような職種といえるでしょう。

交通巡視員のおもな業務は、以下のとおりです。
交通巡視員は、警察官同様に警察の採用試験を受けて採用されます。採用は各都道府県警察が行ないますが、現在、募集はほとんどありません。
募集があったとしても採用人数は非常に少なく、交通巡視員としての採用を目指すのは現実的に難しいといえるでしょう。

先述のとおり、交通巡視員の求人はほぼありません。交通整理系の仕事に就きたいなら、仕事内容が似ている交通誘導警備員を目指してみてはいかがでしょうか。
ここでは、交通誘導警備員の概要やおもな仕事内容を紹介します。
道路で交通誘導を行なう人を、交通誘導員と呼びます。交通誘導警備員は、交通誘導員のなかでも交通誘導警備業務検定の合格者か、警備業法に基づいて交通誘導警備の教育を受けた者です。
交通誘導警備員は民間の警備会社に勤めます。そのため、警察官や交通巡視員が行なう交通整理とは異なり、交通誘導警備員の行なう業務には法的拘束力がありません。
交通警備の方法や交通整理との違いについては、下記の記事でも解説しています。併せてご覧ください。
交通誘導警備員のおもな業務は、以下のとおりです。
交通誘導警備員の業務に法的拘束力はありませんが、交通巡視員の業務と同様に、交通の安全性を守る重要な職種といえるでしょう。
※建築・土木等に関連する交通誘導は、SPD株式会社では取り扱っておりません。
交通誘導警備員になるには、警備会社に就職し、該当の業務に就く方法が一般的です。
無資格、未経験でも就職できますが、交通誘導警備業務検定などの資格を保有していると対応できる業務の幅が広がります。資格は就職活動でも有利に働くため、まずは資格取得を目指すのがおすすめです。
また、資格は就職後に取得することもできます。警備会社によっては資格取得のサポートがあるため、希望する場合はサポートの有無もふまえて企業を選びましょう。
なお、18歳未満の方や自己破産手続き中の方などは、警備業法により警備業に就くことができません。
警備業検定には、以下の6種類があります。
| 検定の種別 | 区分 |
| 空港保安警備業務 | 1級及び2級 |
| 施設警備業務 | |
| 雑踏警備業務 | |
| 交通誘導警備業務 | |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務 | |
| 貴重品運搬警備業務 |
警備業務のうち、特定の業務を行なう場合は、警備業務検定に合格した警備員の配置が必要です。交通誘導警備業務では、高速自動車国道または自動車専用道路における業務を行なう場合、1名以上の「交通誘導警備業務検定」の有資格者が必要となります。
資格には1級と2級があり、1級を受検するには2級に合格したのち実務経験を1年以上積まなければいけません。そのため、交通誘導警備にこれから携わるなら、まずは2級取得を目指しましょう。
資格取得方法は、特別講習を受講する方法と、公安委員会が行なう検定を受検する方法の2種類があります。それぞれの概要は以下のとおりです。
公安委員会の登録を受けた機関が実施する特別講習を受ける方法です。
講習修了後に修了考査(学科試験・実技試験)を受け、合格すれば修了証明書が交付されます。修了証明書をもとに検定合格証明書の交付を申請し、検定合格証明書が届けば資格を取得できます。
受講料はかかりますが、講習で必要な知識を確実に得られる点がメリットです。
公安委員会が行なう検定試験(学科試験・実技試験)を受検し、合格すれば資格を取得できます。特別講習よりも費用を抑えられますが、独学で知識を身に付ける必要があります。
なお、交通誘導警備業務2級の取得については、下記の記事でより詳しく解説しています。併せて参考にしてください。
「SPD株式会社」は、創立50年を超える警備会社です。交通警備業務やイベント業務、各種施設への常駐警備業務などを担い、安全・安心な毎日を提供することを使命として業務を行なっています。
交通警備業務では、大規模国際スポーツイベントや大規模な花火大会など、多くのお客様が集まる会場での業務実績があります。鉄道事業者やバス事業者などとも連携しながら、来場者が安心して楽しめる環境づくりをするのが、SPDの役割の一つです。
SPDでは「安心安全な毎日を提供することで、楽しく夢のある社会づくりに貢献する」を使命とし、社員の採用、教育を行なっています。
警備員として長く活躍できるようワーク・ライフ・バランスを重視し、働きやすい環境づくりを目指しています。教育制度も充実しており、新規採用された方への新任教育のほか、実地研修を含む定期的な研修も実施しているため、安心して勤務することが可能です。また、スキルアップに向けた各種資格取得も支援しています。
交通警備業務を担いたい方は、ぜひ一度、SPD株式会社の公式サイトをチェックしてみてください。
交通巡視員は警察職員の一種です。現在は、警察官と統合している都道府県も多く、求人が大幅に減少しており、交通巡視員を目指すのは難しいのが現状です。
交通巡視員のような交通整理系の職種に就きたい方は、交通誘導警備員を目指してはいかがでしょうか。交通誘導警備員は、施設の駐車場や一般道における交互通行の誘導などを行ないます。特定の業務には資格が必要なため、就職活動では、資格取得サポートがある企業を選ぶのがおすすめです。
SPD株式会社では、交通警備を含むさまざまな警備業務を行なっています。仕事とプライベートを両立できる職場環境づくりを目指しており、社内教育支援制度も整っています。交通誘導警備員として働きたい方は、ぜひ採用情報を確認してみてください。
この記事をシェアする

常駐警備とは?業務内容と警備会社へ業務を委託するポイント…

イベント会場等の警備員に必須の雑踏警備2級とは?企業様向…

交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会…

警備会社に警備を依頼する方法は?依頼までの流れやポイント…

警備を依頼したい!業務の種類や料金相場・警備会社を選ぶポ…

警備会社に駐車場管理を依頼する目的とは?依頼先の選び方を…

ガードマンに依頼できる警備業務とは?料金相場や警備会社を…

警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

交通誘導1級と2級の違いとは?取得のメリット・試験内容・…

工場における警備員の業務内容や勤務形態とは?おすすめの警…

警備会社の料金相場は?料金の変動要因や警備会社の選び方も…

交通誘導2級とは?未経験から資格を取得する方法も解説しま…
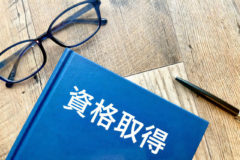
警備業務検定とはどんな資格?取得方法や合格率、メリットな…
関連する記事はありません
